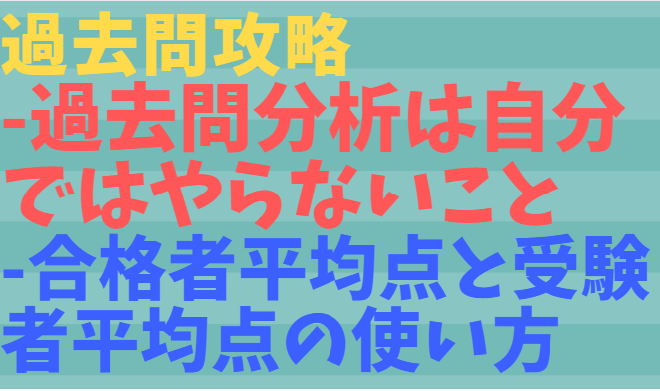
昨日に続いて過去問の記事です。直前期は過去問をやることが多いと思いますが、過去問は人によって千差万別、『過去問に惚れ込む』ぐらいにやりつくす人もいるし、過去問はでないんだからとサクっとやって復習して終わりという人もいます。中学受験生なら必ずやる過去問、自分なりのやり方を見つけるといいと思います。
(1)過去問分析はやらない
過去問を分析して出題傾向を自分で統計とったりとかする人もいますが、基本過去問分析は自分でやる必要はありません。過去問本やインターネット上の分析結果を使いましょう。他人がやった結果を利用する、というのがポイントです。素人があれやこれややるより経験値がある人がやるほうがそりゃいいでしょう。
そのうえで自分でもやりたいという場合は、親がやりましょう。子供に過去問分析をやらせてはいけません。それは子供の仕事ではないと認識しなければいけません。
(2)「セット」と「バラシ」
10年分、15年分と多くの過去問が入手できる場合には、セットとバラシを使い分けるといいでしょう。「セット」と「バラシ」というのは私が勝手にそう呼んでいるだけなので一般用語ではありません。
・「セット」→比較的最近の年度のものは4科目セットで取り扱い、同じ日や同じ週に4科目連続で解く。4科目合計点で合格者最低点を超えるように意識する。など4科目を1セットとして取り扱います。また4科目での得点のバランスなども見ることができる。
・「バラシ」→古い年度の過去問は4科目セットというよりは各科目にわけて考える。国語、算数だけ解いて、理社はやらないとか、苦手分野をピックアップしてやるとか。4科目セットではなく、科目単位、大問単位で取り扱うようにします。古い年度は社会は統計データも古く使いにくいので他の科目のみをバラシで使うなど色々な使い方があります。
セットとバラシの使い方例)
セットで平成30年度分を解く→
算数が受験者平均を下回って対応できていない→
苦手分野と塾のテキストで総ざらい→
バラシで確保してある古い年度の算数だけを解いてみて、結果を確認する→
手ごたえがあったら、29年度を4科目セットで解く。
(3)合格者平均点、受験者平均点
過去問をやるときにどうしても気になるのが合格者最低点です。
これを超えるのがまずは目標になるのではないでしょうか?過去の合格最低点を見つつどのぐらいの得点率で超えるかを意識しておきます。
一般的に、合格最低点を超えるには、合格者平均点と受験者平均点の中間ぐらいをとることが必要になります。科目ごとに、得意科目は合格者平均点、不得意科目は受験者平均点を目標にします。
不得意科目でも、受験者平均点を下回るとなかなか厳しく、特に配点の高い科目で受験者平均を下回ると挽回はなかなか大変です。
(4)わからない問題は積極的に塾の先生に聞く
過去問で心配なのは、声の研究社でも、東京学参にしても解説が貧弱なことです。過去問はほぼ全ての学校で出していること、毎年新しいものがでることから解説の充実は難しいとされています。解答が間違っていることもよくあります。
過去問のなおしのときにわからない問題は塾の先生に聞いていいと思います。復習の必要がなければ、復習は不要とアドバイスされるかもしれません、それはそれで収穫です。
(5)さいごに
過去問はやる量、やり方、やるタイミング、どれが正解というのはないかもしれません。裁断して年度ごとや科目ごとにわけてファイリングするのがいいという方もいます。ご家庭でできる範囲、お子様がやれる範囲でどのように取り組むかご家庭で考えてみるといいと思います。
過去問道は流派が多い、という方は応援クリックお願いします^ ^
↓ ↓ ↓![]()
にほんブログ村